「2020年度」の研究・論文一覧 [ 2/4 ]
-

日本経済(月次)予測(2020年11月)<7-9月期GDP2次速報を更新し、10-12月期実質GDP成長率を前期比年率+7.9%と予測。先週から上方修正>
経済予測
経済予測 » Monthly Report(日本)
/ DATE :
ABSTRACT
※英語版はこちら
-

都道府県別訪日外客数と訪問率:10月レポート
インバウンド
インバウンド
/ DATE :
ABSTRACT
【ポイント】
・JNTO訪日外客数(推計値)によれば、10月総数は27,400人(前年同月比-98.9%)で、13カ月連続のマイナス。10月から一定条件の下、ビジネス等に限って全ての国・地域からの新規入国が可能となったため、2カ月連続で1万人を超える水準となった。
・JNTO訪日外客数(暫定値)を目的別にみれば、8月総数は8,658人(前年同月比-99.7%)となった。うち目的別にみれば、観光客は482人(同-100.0%)、商用客は702人(同-99.4%)、その他客は7,474人(同-96.3%)であった。8月から再入国許可保持者の再入国を一部認めたこともあり、商用客(241人)や留学目的などのその他客(3,123人)が前月から増加した。
【トピックス】
・10月の関空への訪日外客数は前年同月比-99.2%大幅減少し、9カ月連続のマイナス。新たに2府8県ベースで推計(APIR)された2019年の関西での外国人消費額は1兆2,127億円(確報ベース)であるため、20年10月の損失額は1,002億円(= 12,127/12 ×関空への訪日外客数の減少率)と推計される。結果、2-10月期インバウンド需要の損失合計は8,685億円となる。
・10月はビジネスや留学目的の外国人を対象に限定的ではあるが、日本への新規入国が全面緩和された。政府は11月以降、更なる入国緩和を検討しているが、観光目的の入国は依然として厳しく規制されているため、訪日外客の急回復は期待しづらい。
・関西10月の輸出総額の伸びは好調な対中輸出の影響もあり、8カ月ぶりのプラス(前年同月比+2.3%)に転じた。
・8月の関西2府8県の延べ宿泊者数(全体)は7カ月連続の前年同月比マイナス(同-63.3%)。COVID-19の感染再拡大の影響もあり、マイナス幅は前月(同-64.7%)より小幅縮小にとどまった。
・うち日本人延べ宿泊者数をみれば、4,628.7千人泊となり8カ月連続の前年同月比マイナス。外国人延べ宿泊者数をみれば、41.8千人泊となり7カ月連続の前年同月比マイナスとなった。
・8月の延べ宿泊者数(関西2府8県ベース)の減少幅から(関西の)国内旅行消費額の損失額を推計すると、約1,830億円となる(=4.1兆円/12 ×関西の延べ宿泊者数の当月の減少率)。結果、3-8月期の損失額は約1.3兆円となる。
・9月速報値を考慮した延べ宿泊者数(全国ベース)の減少幅から(全国の)国内旅行消費額の損失額を計算すると、約6,840億円となる(=21.9兆円/12 ×全国の延べ宿泊者数の当月の減少率)。結果、3-9月期の損失額合計は約7.3兆円となる。
※英語版はこちら
-

130回 景気分析と予測<民間消費と輸出のリバウンドで見通しを上方修正-しかし、世界経済の回復に遅れる日本経済->
経済予測
経済予測 » Quarterly Report(日本)
/ DATE :
ABSTRACT
1. GDP1次速報によれば、7-9月期実質GDPは前期比年率+21.4%大幅増加し、4四半期ぶりのプラス成長。市場コンセンサス(ESPフォーキャスト11月調査)の最終予測(同+18.03%)を上回った。一方、CQM最終予測は、支出サイドが同+20.3%、生産サイドが同+21.4%、平均同+20.9%と実績とほぼピンポイントとなった。
2. 7-9月期回復の牽引役は、民間最終消費支出と財貨輸出である。前者には緊急事態宣言の解除と特別定額給付金支給の影響がでた。後者には海外経済のロックダウン解除による経済活動再開の影響が大きい。実質GDPは前期比+24.0兆円増加したが、前期の落ち込み幅(-43.0兆円)の58%程度しか回復できていないことに注意。需要側では民間最終消費支出が同+12.6兆円、財貨輸出が同+6.3兆円と増加。ちょうど4-6月期の裏となって表れた。しかし、民間資本形成が同-4.9兆円と2四半期連続で減少しており、回復には時間がかかりそうである。
3. 世帯全体の消費支出を示す総消費動向指数は、6月に緊急事態宣言解除で大きくリバウンドしたが、以降ほぼ横ばいで推移している。一方、対面型サービス消費指数は、足下9月でも前年平均から18%程度低い水準。COVID-19の感染再拡大は消費行動を抑制する。特に影響を受けるのが対面型サービス消費である。対面型サービス消費の低迷で、今後1年、民間消費は前年比-4%程度の減少が続くとみてよい。
4. 7-9月期GDP1次速報を追加し外生変数の情報を織り込み、予測を改定した。2020年度の実質GDPは-5.4%大幅減少し、6年ぶりのマイナス成長となろう。21年度は大幅落ち込みの反動もあり+3.8%と回復に転じるが、コロナ禍前のピークを回復するのは22年度以降となろう。前回(第129回)予測に比して、今回は20年度を+0.5%ポイント、21年度を+0.5%ポイント、いずれも上方修正した。7-9月期の実績が前回予測から上振れたためである。
5. 7-9月期実績は前回予測を上振れたため、今回の予測は上方修正された。実質GDPの四半期パターンをみれば、標準予測では7-9月期の高成長は持続せず(一時的なリバウンド)、以降は潜在成長率を上回るペースが持続する。前年同期比でみると、19年10-12月期から21年1-3月期までマイナス成長は避けられない。大幅に拡大したGDPギャップの縮小には時間がかかりデフレ圧力は厳しい。
6. 内需外需の低迷からデフレ圧力は高まり、厳しい状態が続く。原油安を背景としたエネルギー価格の下落幅は縮小するが、消費税率引き上げ及び幼児教育・保育無償化の影響は剥落し消費者物価を引き下げる。これらに加え、今後の需給ギャップの動向をふまえ、消費者物価コア指数のインフレ率を、20年度-0.4%、21年度+0.5%と予測する。※英語版はこちら
-

Kansai Economic Insight Quarterly No.51:景気は持ち直しているが弱い動きが続く- 感染拡大防止と社会経済活動維持のジレンマ -
経済予測
経済予測 » Quarterly Report(関西)
/ DATE :
ABSTRACT
1. 日本全国の2020年7-9月期実質GDP成長率は前期比年率+21.4%で、4四半期ぶりのプラス成長だった。ただし実質GDPは前期比+24.0兆円増加したが、前期の落ち込み幅(-43.0兆円)の58%程度しか回復できていない。
2. 20年7-9月期の関西経済は、緊急事態宣言解除による反動増や政策効果で持ち直しの動きが見られるが、コロナ禍の収束見通しが立たず、先行き不透明感が強いことから、総じて弱い動きが続いている。
3. 家計部門は、幾分持ち直してはいるものの、コロナ禍前の水準を回復するには至らず、弱い動きが続いている。センチメント、大型小売店販売、所得・雇用環境といずれも底打ちはしているが、コロナ禍の収束の見通しが立たないことから景気の先行き不透明感が強く、回復のペースは緩慢となっている。
4. 企業部門は、生産動向や景況感などで持ち直してはいるものの、水準としてはまだ低いままで、弱い動きが続いている。
5. 対外部門でも、輸出輸入とも弱い動きが続いているが、底打ちの兆しが見られる。特に対中輸出はいち早く回復している。一方インバウンド需要などのサービス輸出は、全面的な入国制限解除がなされていないことから、底ばいが続いている。
6. 関西の実質GRP成長率を2020年度-5.2%、21年度+3.3%と予測する。20年度は記録的な大幅マイナスとなる。21年度には回復に転じるが、コロナ禍前の水準に戻るのは22年度以降となる。
7. 前回予測(8月27日公表)に比べて、20年度・21年度とも実質GRP成長率そのものに修正はないが、各需要項目の成長に対する寄与は、幾分修正している。20年度は、民間最終消費支出および民間住宅を下方修正した一方で、輸出を上方修正した。21年度についても同様に、民間需要を下方修正、域外需要を上方修正した。
8. 需要項目の寄与度を見ると、民間需要-4.7%ポイント、域外需要-0.9%ポイントと成長を押し下げる。公的需要は+0.5%ポイントと成長に貢献するが、民間需要・域外需要の落ち込みを補うには至らない。21年度は、民間需要+1.8%ポイント、公的需要+0.4%ポイント、域外需要+1.1%ポイントといずれも成長に寄与する。
9. トピックスとして、(1)県内GDP早期推計(2019-20年度)と、(2)関西における所得・雇用環境の状況、を取り上げた。※英語版はこちら
-

Kansai Economic Insight Monthly Vol.91- 景気足下は底打ち、先行きは回復の兆し –
経済予測
経済予測 » Monthly Report(関西)
/ DATE :
ABSTRACT
・9月の生産は2カ月ぶりに前月比上昇。結果、7-9月期は2四半期ぶりのプラスだが、水準はコロナの影響が出始めた1-3月期と比べて依然10%程度低く、生産の戻りは遅い。
・9月の完全失業率は4カ月ぶりに前月から改善し、7-9月期は4四半期ぶりの改善となった。しかし、労働力人口や就業者数は感染拡大前の水準(1-3月期)を回復できていない。9月の有効求人倍率(受理地別)は9カ月連続の前月比悪化。7-9月期は5四半期連続の悪化となり、雇用は総じて厳しい状況が続いている。
・8月の関西2府4県の現金給与総額は13カ月連続の前年比減少。また、実質賃金は18カ月連続の同減少。6月を大底としマイナス幅は縮小しているものの、依然所得環境は悪化が続く。
・9月の大型小売店販売額は12カ月連続の前年比減少。新型コロナウイルス感染再拡大の影響と昨年増税前の駆け込み需要による反動を受けて、前月より減少幅が大幅拡大した。
・9月の新設住宅着工戸数は前月比+14.7%と2カ月ぶりに増加した。うち分譲マンションと貸家の寄与が大きい。7-9月期は前期比+2.4%増加し、3四半期ぶりのプラスとなった。
・9月の建設工事出来高は2カ月連続で前年比増加した。結果、7-9月期は小幅ながら10四半期連続の前年比増加となった。10月の公共工事請負金額は5カ月ぶりの前年比減少。
・10月の景気ウォッチャー現状判断DIは6カ月連続で前月から改善。Go To Travelキャンペーンの効果が旅行や小売関連業種の改善に影響したようである。
・10月の輸入の伸びは13カ月連続の前年比マイナスだが、輸出の伸びが8カ月ぶりにプラスに転じたため、黒字幅は同拡大した。対中輸出の回復が大きく寄与した。
・10月の関空の外国人入国者数は、新規入国の条件が一部緩和されたため前月から増加したが、5,381人と依然低水準が続く。
・中国経済は新型コロナウイルスの影響を克服しつつある。10月の貿易総額は5カ月連続で拡大し、工業生産の伸びは2カ月連続でコロナ禍直前と同程度まで回復。一方、消費の伸びは未だ昨年12月を回復していないが、電子商取引は好調が続いている。※英語版はこちら
-

後期高齢者医療費の自己負担割合のあり方- 今年末に取りまとめられる所得基準の線引きに向けて –
インサイト
インサイト » トレンドウォッチ
/ DATE :
ABSTRACT
1. 我々が病院や診療所で受診した場合、医療費の窓⼝負担(⾃⼰負担)が必要になる。現⾏制度では、現役世代は所得に関係なく3割負担、70〜74歳の⾼齢者は原則2割負担であるが、75歳以上の後期⾼齢者は原則1割負担となっている。⾼齢者でも現役並み所得がある場合は3割負担となる。
2. 2022年から団塊の世代が75歳以上の後期⾼齢者に⼊り始め、医療費が急増していく⼀⽅で、⽀え⼿の現役世代の⼈⼝は急減が⾒込まれると想定される中で、現役世代の負担上昇を抑えながら、医療保険制度の持続性を維持する観点から、後期⾼齢者医療費の⾃⼰負担割合を負担能⼒に応じて2割に引き上げる議論が進んでいる。政府の全世代型社会保障検討会議などでは、⼀定以上の所得がある⼈には⾃⼰負担割合を2割に引上げる⽅針であり、焦点となる所得基準の線引きの議論を本年末までに⾏うとし、⼤詰めの段階に来ている。
3. 今後も現役世代が⾼齢者医療を⽀えていく必要があるが、医療保険制度を維持し、増⼤する⾼齢者医療費を現役と⾼齢の両世代でなるべく公平に負担を分かち合うためには、「能⼒に応じて」という意味で、⼀定以上の所得がある⾼齢者については、⾃⼰負担割合を引上げることはやむを得ない。⼀⽅、⾼齢者側の事情も⼗分に踏まえる必要がある。1⼈当たり医療費は年齢階級が上がるほど増えていく。⾼齢者は平均年収も⼀般的に下がるので、年間所得に対する患者の窓⼝負担額の割合は現役世代より⾼い。所得が低いほど負担が逆進的になる。
4. そもそも、所得基準の線引きについては、明確な根拠を求めることは難しいが、筆者の考えとしては、所得額に応じて利⽤者負担割合が1割、2割、3割とすでに分けて設定されている介護保険サービスを参考にしてはどうかと考える。後期⾼齢者医療費の⾃⼰負担割合引上げについては、まずは、合計所得160万円以上(年⾦収⼊等約280万円以上)の⼀般所得者を対象に2割負担を導⼊するのが適当と考える。その導⼊タイミングは、急な制度変更で混乱が⽣じないよう、2022年4⽉以降に75歳になる⾼齢者から順次適⽤していくのがよいだろう。
5. また、将来的な検討課題となるが、「能⼒に応じて」の負担という中には⾦融資産や不動産の保有状況も反映させることが考えられる。例えば、フローの年間収⼊は少なくても多額の⾦融資産や不動産を保有する⾼齢者には3割負担を求めることは検討に値するだろう。
-
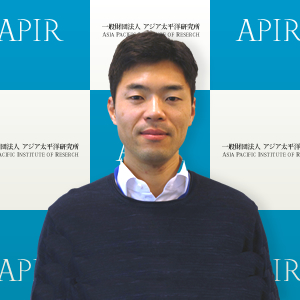
テキストデータを利用した新しい景況感指標の開発と応用(上) ― 入門編:基礎的概念と分析手法の解説 ―
ディスカッションペーパー
ディスカッションペーパー
/ DATE :
ABSTRACT
本稿では、テキストデータを用いて数量的考察を行う際の基礎的概念を紹介し、同データを用いて経済動向を分析する際の基本的な手続きについて、入門レベルの解説を行います。テキストデータとは、新聞や書籍に書かれるような文字列で表されている情報を数値化したものであり、経済のみならず様々な分野において新たなデータソースとして注目を集めています。ここでは、テキストデータの特徴、テキストマイニングの基本的手続きを平易に解説します。続いてテキストマイニングを用いることは、経済動向を理解する上で、有用な手法であることを説明します。
後半では、内閣府の「景気ウォッチャー調査」のテキストデータを用いた簡単な分析結果を示し、テキストデータを用いた経済分析の一例を紹介し、経済分析においてテキストマイニングを用いることの難しさについても検討します。 -

インバウンド需要におけるキャッシュレス決済についての分析 -「関西における訪日外国人旅行者動向調査事業」アンケート調査から-
インサイト
インサイト » トレンドウォッチ
/ DATE :
ABSTRACT
本稿では、「関西における訪日外国人旅行者動向調査事業」アンケート調査に基づいて、関西のインバウンド需要とキャッシュレス決済との関係を様々な角度から分析を行った。
本アンケート調査から得られた興味あるfindingsは以下の通りである。
①キャッシュレス決済の利用頻度や形態は国・地域によって異なり、欧州や北米からの訪日外国人客(以下、訪日外客)はクレジットカード利用が多い一方で、中国人は現金もしくはQRコードの利用頻度が高い。
②キャッシュレス決済の利便性について、多くの訪日外客が交通機関や買い物・飲食代支払い時に十分享受していないと感じているようである。また場所別では、飲食店やホテルではおおむね使いやすいと感じているが、バス等の交通機関や寺社仏閣や美術館などにおいては不便であると感じている割合が高い。
③なお、本アンケートでは訪日外客に旅程を通じて為替レートを意識しているか否かも質問している。回答結果は「旅マエ」までは為替レートをある程度意識するが、「旅アト」時には意識しないと答える割合が高くなる傾向がみられた。訪日外客は「旅アト」において今回の旅行を振り返るとすれば、滞在中(「旅ナカ」)においてキャッシュレス決済で財・サービスを購入する際にあまり為替レートを意識しなかった、という興味深い情報を本アンケートは提供していることになる。
今回のアンケート調査は、地域を関西に限定しているが、今後インバウンド需要を促進していくためにも、我が国のキャッシュレス決済をより一層充実させていくことが不可欠であることを示唆している。
-

日本経済(月次)予測(2020年10月)<GDP推計の基礎データがほぼ揃う。7-9月期実質成長率を支出・生産両サイドともに年率+20%程度と予測>
経済予測
経済予測 » Monthly Report(日本)
/ DATE :
ABSTRACT
※英語版はこちら
-

Kansai Economic Insight Monthly Vol.90- 景気は足下・先行きともに底打ちの兆し –
経済予測
経済予測 » Monthly Report(関西)
/ DATE :
ABSTRACT
・8月の生産は前月比横ばい。水準は今年の生産のピークである1月と比較すると11%低く、生産の戻りは遅い。
・8月の完全失業率は前月比横ばい。一方、同月の有効求人倍率は8カ月連続の同悪化。就業地別では0.98倍と2014年4月以来の1倍を割り込む低水準となった。雇用は総じて厳しい状況が続く。
・7月の関西2府4県の現金給与総額は12カ月連続の前年比減少。就業時間調整やテレワーク推進で所定外労働時間は減少傾向。実質賃金は17カ月連続の同減少。所得環境は悪化が続く。
・8月の大型小売店販売額は11カ月連続の前年比減少。新型コロナウイルスの感染再拡大や猛暑により外出を控える動きが強まり、消費の回復は小幅にとどまった。
・8月の新設住宅着工戸数は前月比大幅減少し、2カ月ぶりのマイナス。うち貸家と分譲マンションの寄与が大きい。
・8月の建設工事出来高は2カ月ぶりに前年比増加した。9月の公共工事請負金額は4カ月連続の同増加となった。
・9月の景気ウォッチャー現状判断DIは5カ月連続で前月比改善。百貨店などの小売関連業種やGo To Travelキャンペーンで旅行関連業業種の改善が影響したようである。
・9月の輸出額は7カ月連続の前年比マイナスだが、減少幅は4カ月連続で縮小。対中輸出の回復と対米輸出の改善が影響した。一方、輸入額は12カ月連続の同マイナス。
・9月の関空の外国人入国者数は在留資格をもつ外国人の再入国が全面緩和されたこともあり、前月から幾分増加したものの、依然低水準が続いている。
・中国の7−9月期の実質GDPは前年同期比+4.9%と4-6月期から加速。また、1-9月期の累積ベースでは前年比+0.7%とすでに前年の水準を上回っており、通年ではプラス成長が予想される。※英語版はこちら
-

都道府県別訪日外客数と訪問率:9月レポート
インバウンド
インバウンド
/ DATE :
ABSTRACT
【トピックス】
・3-7月期の宿泊者数(関西2府8県ベース)の減少幅から国内旅行消費額の損失額を推計すると約1.1兆円となる(= Σ4.1兆円/12 ×関西の延べ宿泊者数の各月の減少率)。
また、8月速報値を考慮した3-8月期の宿泊者数(全国ベース)の減少幅から国内旅行消費額の損失額を計算すると約6.6兆円となる(= Σ21.9兆円/12 ×全国の延べ宿泊者数の各月の減少率)。
・7月の関西2府8県の延べ宿泊者数(全体)は6カ月連続の前年同月比マイナス(同-64.7%)。各府県とも経済活動の再開により、前月から宿泊者数は幾分増加したが、感染再拡大の懸念もされているため、水準は低調である。
・うち日本人延べ宿泊者数をみれば、3,679.9千人泊となり7カ月連続の前年同月比マイナス。外国人延べ宿泊者数をみれば、66.4千人泊となり6カ月連続の前年同月比マイナスとなった。
・関西9月の輸出は前年同月比-5.7%と7カ月連続のマイナスだが、対中輸出の回復と対米輸出の改善もあり、輸出は引き続き改善の兆しがみられる。
・9月の関空への訪日外客数は前年同月比-99.6%大幅減少し、8カ月連続のマイナス。新たに2府8県ベースで推計(APIR)された2019年の関西での外国人消費額は1兆2,127億円(確報ベース)となった。このため9月のインバウンド需要の損失額は1,006億円(= 12,127/12 ×関空への訪日外客数の減少率)と推計される。
・9月は再入国者に対する入国が全面的に緩和されたが、大幅な落ち込みが続いている。10月以降、ビジネス関連を中心とした外国人の入国緩和が行われる予定だが、観光目的の入国に対しては引き続き厳しい入国規制がされているため、訪日外客の急回復は期待しづらい。
【ポイント】
・9月の関西2府8県別に訪日外客数(推計値)をみると、福井県19人、三重県94人、滋賀県105人、京都府3,905人、大阪府4,597人、兵庫県766人、奈良県1,460人、和歌山県143人、鳥取県49人、徳島県32人となった。各府県の伸び率は前年同月比-99%程度で依然厳しい状況が続いている。
・JNTO訪日外客数推計値によれば、9月総数は13,700人(前年同月比-99.4%)となり、12カ月連続のマイナスだが、9月から一部の国でビジネス目的の入国者の往来再開や在留資格をもつ外国人の再入国が緩和されたため、6カ月ぶりに1万人を超える水準となった。
※英語版はこちら
-

新型コロナウイルス対策特別会計(仮称)の設置 -予算・執行の透明化と財政規律の確保を求める-
インサイト
インサイト » トレンドウォッチ
/ DATE :
ABSTRACT
新型コロナウイルスは、海外で依然猛威をふるっている。国内においても、今後、インフルエンザとの同時流⾏や感染流⾏の「第3波」の可能性があり、警戒は怠れない状況にある。新型コロナウイルスは、わが国の財政の悪化にも⼤きな影響を及ぼしている。コロナ禍の出⼝は未だ⾒通せず、財政⾚字の⼤幅な増加が今年度だけで終わる保証はない。
もちろん、新型コロナウイルス対応は、国⺠の⽣命と経済社会を守るためのものであり、必要な歳出は躊躇なく機動的に⾏うことが必要である。しかし、財政規律のタガがはずれたままであってよいわけはない。財政⺠主主義の原則に照らし、緊要な予算・執⾏でも透明性の確保と事後の効果検証は必要であるし、緊急事態から脱したときから、財政健全化に向けてどのような取り組みを⾏うかも今から議論・検討しておくべき重要課題と考える。そこで、今後の財政健全化に向けては、平時と緊急時で分けて考えていくことを提案したい。提案内容の要約は、以下の通りである。
1. コロナ禍前からのわが国財政は、社会保障の給付と負担のアンバランスなどによる構造的な財政⾚字を抱えており、こうした平時の財政の健全化については、潜在成⻑率を引上げ、経済成⻑を通じた税収増による財政収⽀改善が重要であるとともに、社会保障⽀出増加の抑制に踏み込んだ改⾰、消費税による安定的な税財源の確保が必要と考える。
2. ⼀⽅、新型コロナウイルス対応に要した緊急の歳出については、東⽇本⼤震災復興特別会計にならい、別途、「新型コロナウイルス対策特別会計(仮称)」を設置して、事業に時限を付しつつ、予算・執⾏を⼀元的に管理し透明化するとともに、その財源充当のために発⾏した国債全額は、コロナ危機からの経済回復後の特別増税などにより計画的に償還していくことが必要と考える。コロナ禍の今を⽣きる世代が連帯して負担し、将来世代に負担を先送りしないとして、借換債も含め全体として20年間で償還し終えるのが適切と考える。
3. 新型コロナウイルス対策で発⾏した国債の償還財源については、負担の分かち合いや能⼒に応じた追加負担という意味で、所得税が最も望ましい。特に、コロナ禍でも所得減の影響が少なかった(あるいは、影響がなかった)中・⾼所得者に特別な負担を求めることは公平の観点から妥当であろう。これに加え、社会連帯と経済対策の受益という意味で、法⼈も幅広く負担することが必要だろう。さらに、国際協調により資産課税や⾦融取引課税を主要国が同時に同税率で導⼊することもめざすべき⽅策であろう。
-

日本経済(月次)予測(2020年9月)<企業設備の関連指標は依然低迷、7-9月期実質GDP成長率の回復は前期の落ち込みに対して戻りが遅い>
経済予測
経済予測 » Monthly Report(日本)
/ DATE :
ABSTRACT
※英語版はこちら
-

Kansai Economic Insight Monthly Vol.89- 景気は足下・先行きともに底打ちの兆し –
経済予測
経済予測 » Monthly Report(関西)
/ DATE :
ABSTRACT
・7月の生産は2カ月連続の増産。水準は4月まで回復したものの、1-3月期平均比10%程度低い。主に増産となったのは、汎用・業務用械工業、電気・情報通信機械工業等であった。
・7月の完全失業率は2カ月連続の悪化。企業業績の悪化を受け、解雇や雇い止めが増加した。また、同月の有効求人倍率は7カ月連続の悪化、新規求人倍率は2カ月連続の悪化であった。
・6月の関西2府4県の現金給与総額は名目で11カ月連続の前年比減少。就業時間調整やテレワークの推進で所定外労働時間は減少傾向にある。実質賃金は16カ月連続の同減少。所得環境は悪化が続いている。
・7月の大型小売店販売額は10カ月連続の前年比減少。新型コロナウイルスの感染再拡大による外出自粛、長雨の天候不順などの影響によって、消費の回復は足踏みしている。
・7月の新設住宅着工戸数は小幅増加し、2カ月ぶりの前月比増加。うち貸家と分譲マンションの寄与が大きい。
・7月の建設工事出来高は2カ月ぶりの前年比減少となった。8月の公共工事請負金額は3カ月連続の増加となった。
・8月の景気ウォッチャー現状判断DIは4カ月連続で前月比改善。新型コロナウイルス感染再拡大のペースが鈍化したことが影響したようである。
・8月の貿易収支は7カ月連続の黒字となったが、輸出入いずれも前年比減少したため、貿易総額は11カ月連続の減少。なお、輸出では鉱物性燃料が減少し、輸入では原粗油が減少した。
・8月の関空への外国人入国者数は在留資格をもつ外国人に対する再入国の条件が一部緩和されたこともあり、前月から幾分増加したものの、低水準が続いている。
・8月の中国経済は回復が続いている。消費や輸出は改善している。一方、投資は依然として前年比マイナスが続いている。早期にCOVID-19の感染拡大を封じ込めたものの、世界的に再拡大が懸念されており、先行きは引き続き注意を要する。※英語版はこちら
-

都道府県別訪日外客数と訪問率:8月レポート
インバウンド
インバウンド
/ DATE :
ABSTRACT
【トピックス】
・3-6月期の宿泊者数(関西2府8県ベース)の減少幅から国内旅行消費額の損失額を推計すると約0.9兆円となる(= 4.1兆円/12 ×関西の延べ宿泊者数の各月の減少率)。
また、7月速報値を考慮した3-7月期の宿泊者数(全国ベース)の減少幅から国内旅行消費額の損失額を計算すると約5.7兆円となる(= 21.9兆円/12 ×全国の延べ宿泊者数の各月の減少率)。
・6月の関西2府8県の延べ宿泊者数(全体)は5カ月連続の前年同月比マイナス(同-74.4%)。全国を対象に5月25日に緊急事態宣言が解除され、6月19日に都道府県をまたぐ不要不急の移動も緩和されたことで、日本人宿泊者が幾分増加したようである
・うち日本人延べ宿泊者数をみれば、2,414.8千人泊となり6カ月連続の前年同月比マイナス。外国人延べ宿泊者数をみれば、44.2千人泊となり5カ月連続の前年同月比マイナスとなった。
・関西8月の輸出は前年同月比-8.7%と6カ月連続のマイナスだが、対中輸出の伸びもありマイナス幅は3カ月連続で縮小。輸入額は同-17.0%減少し11カ月連続のマイナス。引き続き対欧米向けの輸出が減少していることに加え、中東からの原油や原粗油の輸入の減少も影響した。
・8月の関空への訪日外客数は前年同月比-99.8%大幅減少し、7カ月連続のマイナス。新たに2府8県ベースで推計(APIR)された2019年の関西での外国人消費額は1兆2,127億円(確報ベース)となった。このため8月のインバウンド需要の損失額は1,008億円(= 12,127/12 ×関空への訪日外客数の減少率)と推計される。
・8月は再入国者に対する入国緩和も一部行われたが、落ち込みは前月とほぼ同程度であった。9月以降、在留資格をもつ外国人に対する再入国も徐々に緩和されるが、依然として厳しい入国規制がとられているため、訪日外客の急回復は期待しづらい。
【ポイント】
・8月の関西2府8県別に訪日外客数(推計値)をみると、福井県12人、三重県58人、滋賀県67人、京都府2,485人、大阪府2,854人、兵庫県474人、奈良県808人、和歌山県74人、鳥取県28人、徳島県20人となった。各府県の伸び率をみれば、前年同月比-99%程度の減少となっている。
・JNTO訪日外客数推計値によれば、8月総数は8,700人(前年同月比-99.7%)となり、11カ月連続のマイナス。ビジネス目的での長期滞在者の往来再開や在留資格をもつ外国人の再入国が一部緩和され、前月から幾分増加したが、低水準が続いている。
※英語版はこちら
-

水災害の激甚化への総合的対策の強化- 全国的な対策推進の枠組み、土地利用規制、保険制度の強化を-
インサイト
インサイト » トレンドウォッチ
/ DATE :
ABSTRACT
近年、全国各地で豪⾬等による⽔災害が頻発し、被害も甚⼤化するケースが増えている。限られた財政の中では、堤防強化や砂防⼯事などの公共事業によるハード対策だけに頼るには限界がある。⽔災害リスクを低減させる⼟地利⽤、実効性ある避難態勢の構築などのソフト対策もあわせて推進していく必要がある。国としても、2020年度からハード・ソフト⼀体の「流域治⽔」という総合的対策の強化に舵を切っている。こうした国の動きは⾼く評価できるが、効果をさらに⾼めるためには、地震対策と同じような総合的対策の枠組みの強化、浸⽔ハザードエリアでの⼟地利⽤のさらに踏み込んだ規制、⾃助を促す⽔災害保険の強化が、なお必要な課題と考える。これら課題への対応策として、本稿において提案する内容の要約は、以下の通りである。
1. 地震対策では「地震防災対策特別措置法」が制定され、国と地⽅あげた全国的な防災対策の強⼒な推進の枠組みがあるが、⽔災害対策では⽤意されていない。近年の激甚化する⽔災害で顕在化した課題への対応をはじめ、全国的な⽔災害対策の強⼒な推進のため、国は「⽔災害対策特別措置法」(仮称)を制定し、全都道府県において優先度も踏まえた実施⽬標の設定と5年おきの事業計画を策定し、進捗管理のPDCAを回す枠組みの早期具体化を期待する。
2. ⽔災害リスクの⾼い地域では、現⾏法上、⼀部開発許可の厳格化があるものの、警戒・避難態勢の整備を求めるにとどまる。浸⽔ハザードエリアすべてにおいて、新たな開発規制を課すことは現実的でない。浸⽔深が深く浸⽔継続時間が⻑いと想定される地域や家屋倒壊等氾濫想定区域といった特にリスクの⾼いエリアでは、新たな開発を原則禁⽌とすべきと考える。
3. ⾃助による保険の備えは、⽔災害の被災者の住宅再建で重要な役割がある。甚⼤化する⽔災害は今後も続く可能性が⾼く、⺠間損害保険会社の保険⾦⽀払負担⼒の余⼒が激減している。⼤都市の⼤河川の氾濫ともなれば、⼀気に限界に達しかねない。先⾏する地震保険と同じように、⺠間の負担⼒を超えるところは国が再保険を⾏い、官⺠が保険責任を分担する⽔災害保険制度を整備する時に来ているのではないだろうか。この新しい保険制度では、損害補償だけの機能にとどまらせず、住⺠・企業等に⽔災害リスクを認識させ防災意識を⾼めるとともに、危険な⼟地の開発禁⽌といった適切な⼟地利⽤や地域の防災・減災努⼒と連携するような制度設計を⾏う必要がある。保険料にリスクの⾼低を反映させ、住⺠や地域等の防災・減災努⼒に応じて保険料の割引を受けられるインセンティブとあわせたものとすべきである。
-

訪日外国人消費による関西各府県への経済効果: 2018-19年比較
インサイト
インサイト » トレンドウォッチ
/ DATE :
ABSTRACT
2019年各種統計の確報値(訪日外客統計、訪日外国人消費動向調査、宿泊旅行統計調査報告)に基づき、「2011年版APIR関西地域間産業連関表」を用いて、訪日外国人消費の関西経済に与える影響を分析した。得られた結論は以下のように要約できる。
(1)2019年の訪日外客数の伸びは、18年の前年比+8.7%から同+2.2%に減速した。その最大の要因は韓国からの訪日客の激減である(同-25.9%)。
(2) 国籍別では、2019年の中国からの訪日客は約959万人と全体の3割を占めており、日本の訪日外客はアジア(特に中国)に偏在した構成となっている。なお、関西をみれば、中国のシェアは43.4%と全国と比べて高く、関西の訪日外客は中国が突出した構図となっている。
(3) 2019年訪日(関西)外客の観光消費額を18年と比較すると、関西2府8県では14.4%増加した。うち、京都府の伸び(+42.8%)が群を抜いて高く、福井県(+14.5%)、徳島県(+9.8%)、三重県(+7.6%)がこれに続いている。一方、和歌山県(-8.7%)、鳥取県(-1.5%)は減少した。
(4)観光消費額の経済(粗生産、付加価値、雇用)への波及を府県別にみると、2019年で最も高い伸びを示したのが京都府であり、他の9府県と比べて圧倒的な差をつけている。
(5)訪日外国人消費の関西名目GRPに対する寄与度は、2017年に初めて1%を超え、2018年は関空被災にも関わらず1.08%となり、19年は1.25%と加速した。うち、京都府では中国人客の増加もあり、19年の寄与度は大幅に上昇した(1.80%→2.54%)。大阪府は上昇したものの、韓国人客の減少もあり、寄与度の伸びは小幅にとどまった(1.35%→1.47%)。
(6) コロナ禍の影響により、2020年前半の訪日外客数はほぼ絶無であり、20年の訪日外国人消費は絶望的である。19年関西2府4県の訪日外客観光消費による付加価値波及は1兆678億円で、仮にこれがすべて消失すると、19年の関西名目GRPを1.23%押し下げることとなる。
-

日本経済(月次)予測(2020年8月)<8月の統計発表集中日データを更新した結果、7-9月期実質GDP成長率予測は前期比年率+12.1%>
経済予測
経済予測 » Monthly Report(日本)
/ DATE :
ABSTRACT
※英語版はこちら
-

Kansai Economic Insight Quarterly No.50 – COVID-19の感染拡大で記録的な景気減速:対中輸出は早期回復しているがリスク孕む –
経済予測
経済予測 » Quarterly Report(関西)
/ DATE :
ABSTRACT
1. 2020年4-6月期の関西経済は、COVID-19の感染拡大とそれに伴う緊急事態宣言の発令から、急速に悪化した。足下では宣言解除による反動増や政策効果で底打ちの兆しもみられるが、基調としては弱く、厳しい状況が続く。全国の4-6月期実質GDP成長率は前期比年率-27.8%で、3四半期連続のマイナス成長だった。
2. 家計部門は、厳しい状況が続いている。センチメントや大型小売店販売は、COVID-19の感染拡大と緊急事態宣言発令により急激に悪化した。足下で下げ止まっているが、コロナ禍前の水準には及ばない。所得・雇用環境は昨年来から弱含みだったところへ、コロナ禍で一段の悪化となった。
3. 企業部門は、生産動向、景況感ともに急速に悪化している。20年度の設備投資計画は堅調であるが、設備の過剰感が強まっており、下方修正となる可能性が高い。
4. 対外部門も、弱い動きとなった。財貨の貿易は輸出・輸入ともに縮小が続いている。対中輸出には回復の兆しが見られるが、カントリーリスクを孕む。インバウンド需要などのサービス輸出は、消失したままである。
5. 関西の実質GRP成長率を2020年度-5.2%、21年度+3.3%と予測する。20年度は記録的な大幅マイナスとなる。21年度には回復に転じるが、以前の水準に戻るのは22年度以降となる。
6. 前回予測(5月28日公表)に比べて、20年度は-0.1%ポイントの下方修正、21年度は+0.7%ポイントの上方修正である。20年度は、民間企業設備の見込みを上方修正した一方で、域外需要について純輸出・純移出とも下方修正した結果、全体では小幅下方修正となった。21年度は域外需要を上方修正とした。7. 2020年度は民間需要と域外需要がそれぞれ-4.4%ポイント、-1.1%ポイントと大きく成長を抑制する。公的需要は+0.3%ポイントと成長に貢献するが、民間需要のマイナスを補うには至らない。21年度は、民間需要+2.1%ポイント、公的需要+0.3%ポイント、域外需要+1.0%ポイントといずれも成長に寄与する。
8. 関西経済は中国とのつながりが強く、足下でも対中輸出が早期回復しているが、チャイナ・リスクが懸念材料である。標準予測に対するリスク要因として、COVID-19の収束時期、米中対立の行方、長江流域の水害を指摘する。
9. トピックスとして、(1)2019年訪日外国人消費の経済効果の推計と、(2)関西経済予測10年間の振り返り、を取り上げた。 -

129回 景気分析と予測<COVID-19感染再拡大と景気回復のバランス:難解なパズルの解を求めての試行錯誤>
経済予測
経済予測 » Quarterly Report(日本)
/ DATE :
ABSTRACT
1. 8月17日発表のGDP1次速報によれば、4-6月期実質GDPは前期比年率-27.8%(前期比-7.8%)減少し、3四半期連続のマイナス成長。市場コンセンサス(ESPフォーキャスト8月調査)最終予測(同-26.59%)とほぼ同程度であった。CQM最終予測は、支出サイドが同-25.0%、生産サイドが同-20.2%、平均同-22.6%となった。
2. 4-6月期に、国内総生産(実質GDP)は前期比-41.1兆円大幅減少したが、需要側では民間最終消費支出と財貨の輸出の減少がこれに対応した。緊急事態宣言による影響が民間最終消費支出に、ロックダウンによる海外経済停滞の影響が財貨の輸出減に出たといえよう。一方、1-3月期は、前期比-3.3兆円の国内生産減少と中国の生産停止による財貨輸入の減少に対して、需要側ではサービス輸出、民間最終消費支出、財貨の輸出の減少が対応した。
3. 新たに認定された暫定的な山(2018年10月)からの今回の景気後退は、緊急事態宣言の解除により5月に底打ちした可能性も出てきた。しかし、経済活動の再開に伴い第2波の感染再拡大が起こっている。今後も続く感染拡大と景気回復のバランスという難解なパズルにとって、ソーシャルディスタンス(社会的距離)の確保が必須で、これが今後の日本経済の回復を緩やかなものにとどめる。
4. 4-6月期GDP1次速報を追加し外生変数の情報を織り込み、予測を改定した。2020年度の実質GDPは-5.9%大幅減少し6年ぶりのマイナス成長となろう。21年度は大幅落ち込みの反動もあり+3.3%と回復に転じるが、コロナ禍前のピークを回復するのは22年度以降となろう。前回(第128回)予測に比して、今回は20年度を-0.3%ポイント下方修正。21年度を+0.8%ポイント上方修正した。
5. 月次指標から明らかなように、景気は5月に大底を打っており、6月は大幅な改善を示している。実質GDPの四半期パターンをみれば、7-9月期は前期比年率10%を超える成長を予測する。ただ高成長は持続せず一時的なリバウンドにとどまり、以降は潜在成長率を上回るペースが持続するが、前年同期比でみると、19年10-12月期から21年1-3月期までマイナス成長は避けられない。
6. 19年10-12月期にマイナスに転じたGDPギャップはしばらく悪化をたどる。内需外需の低迷からデフレ圧力は高まり深刻。原油安を背景としたエネルギー価格の下落幅は縮小するが、幼児教育無償化に加え高等教育無償化の影響はCPIを引き下げる。これらに加え、今後の需給ギャップの動向をふまえ、消費者物価コア指数のインフレ率を、20年度-0.3%、21年度+0.4%と予測する。※英語版はこちら

