村上副主任研究員が神戸新聞より取材・紙面掲載

DATE: 2013-01-05
「「一票の力」への実感が鍵」
林研究統括、稲田研究統括が日本経済新聞・経済教室に寄稿
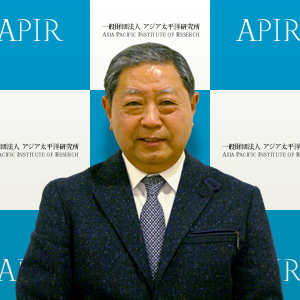
DATE: 2013-01-21
「安倍政権 経済政策の課題④ 公共投資より雇用対策を」
林研究員の論文が『北京規劃建設』,108-112に掲載
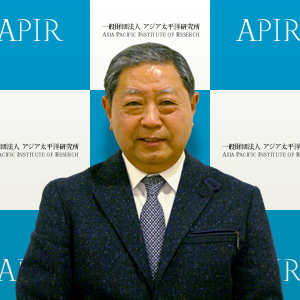
DATE: 2013-01-01
「南海トラフ巨大地震による経済被害の計算」
「関西エコノミックインサイト」最新の関西経済見通しを発表

DATE: 2010-12-02
関西社会経済研究所(所長 本間正明)の関西経済予測モデル(監修:甲南大学稲田義久教授・関西学院大学高林喜久生教授)による、最新の「関西経済予測」を発表した。
関西の実質GRP成長率を2010年度+2.6%、2011年度+1.6%、2012年度+1.4%と予測した。補正予算の効果を反映したため、前回予測より上方修正である。
掲載メディア
- 日本経済新聞、朝日新聞、産経新聞、毎日新聞、読売新聞
最新の日本経済見通しを発表

DATE: 2010-11-24
日本経済の改訂見通しを受けて、財団法人関西社会経済研究所(所長 本間正明)では、最新の「日本経済四半期予測」を発表した。
7-9月期GDP速報値を受け、2010年度実質GDP成長率を+3.0%、2011年度+1.6%、2012年度を+1.6%と予測。
前回から2010年度は0.8%ポイント上方修正、2011年度は0.1%ポイントの下方修正となった。
さらに2010年度補正予算を含む緊急経済対策の効果を、2010年度+0.38%、2011年度+0.53%と予想した。
「韓国における電子徴税システム、電子申告システムに関するヒアリング調査研究」結果をプレス発表

DATE: 2010-10-03
10月4日、「韓国における電子徴税システム、電子申告システムに関するヒアリング調査研究」結果をプレス発表しました。
「2010年版関西経済白書」を発表

DATE: 2010-09-07
2010年9月8日 「2010年版関西経済白書」を発表しました。
財団法人関西社会経済研究所はこの度、「2010年版 関西経済白書?関西らしさの繁栄に向けて?」を発行しました。2010年版白書は、2部構成になっており、第Ⅰ部は「金融危機からの脱出と関西発展の可能性」と題し、当面の関西経済を予測するとともに、第2章で、関西の発展基盤となる自治体の企業誘致策について立地魅力を分析しています。
第Ⅱ部は、「関西発展戦略」と題し、激動する世界経済の中で関西が生き残り、発展するためのソリューションビジネスとして、第3章で住宅投資、第4章で環境ビジネスを取り上げ関西の特徴および可能性を論じています。さらに、第5章では、発展の基盤となる自治体財政の健全性と生産性を検証し、持続的な自治体運営における広域連携の重要性を説いています。
9月15日、政府刊行物センター及び関西の大手書店(旭屋書店、紀伊国屋書店、ジュンク堂書店など31店舗)で発売。
定価2,500円(税込み)
掲載メディア
- 日本経済新聞、朝日新聞、産経新聞、毎日新聞、読売新聞、神戸新聞、建通新聞、日刊工業新聞
「関西エコノミックインサイト」最新の関西経済見通しを発表

DATE: 2010-08-31
関西社会経済研究所(所長 本間正明)の関西経済予測モデル(監修:甲南大学稲田義久教授・関西学院大学高林喜久生教授)による、最新の「関西経済予測」を発表した。
関西の実質GRP成長率を2010年度+2.0%、11年度+1.4%と予測。
2010年度の成長率寄与度は、民需が+0.9%ポイント、外需が+1.1%ポイントで、これらがバランスよく関西経済の成長を支えるが、2011年度はやや外需の寄与が減速すると予測している。
掲載メディア
- 日本経済新聞、朝日新聞、産経新聞、読売新聞、毎日新聞
最新の日本経済見通しを発表

DATE: 2010-08-23
日本経済の改訂見通しを受けて、財団法人関西社会経済研究所(所長 本間正明)では、最新の「日本経済四半期予測」を発表した。2010年度の実質GDP成長率は+2.2%、2011年度+1.7%と予測。前回から2010年度は0.6%ポイント下方に、2011年度は0.3%上方に修正された。
下方修正の理由としては、2010年度への成長率のゲタが0.2%ポイント下がったこと、民需の見通しが前回から下方修正されたためである。
掲載メディア
- 日本経済新聞、産経新聞、毎日新聞、読売新聞

